こんにちは。これから不定期連載「イカ沼通信」をお届けする、イカ愛好家の佐野まいけると申します。
さて、名乗るなり質問で恐縮だが、皆さんイカを食べるのは好きだろうか。大好きとまではいかなくても、嫌いな人は少ないのではないか。日本では刺身や焼きイカ、イカめし、イカフライなどの総菜に加え、コンビニやスーパーのつまみコーナーはもはやイカコーナーと言ってもよいほどイカの加工品が並んでいる。日本人の多くはイカ好きと言えるだろう。

みんな大好きイカの一夜干し
しかし、イカには人生を変えてしまうほどの力がある、と言ったら信じるだろうか。「たかがイカで」と思うかもしれないが、本当のことだ。その証拠がこの私である。
食べ物から生き物へ 視点の変化
きっかけは10年以上前に葛西臨海水族園で出会ったアオリイカである。当時は仕事最優先の生活だったこともあり生き物にもさほど興味がなく、あらゆる水槽は背景でしかなかった。そんな中、なぜか目に留まったのがアオリイカ水槽。
近づいてみると、そこで泳ぐ生き物は私の知っているイカとは程遠い姿だった。透き通り、腕を優しく開いたり閉じたりしながらホバリングする姿はバレリーナのよう。目の上はアイシャドウを塗ったように青や緑に輝いている。イカとはこんなに美しい「生き物」だったのか!驚きと興奮で我を忘れるあまり、同行者の存在まで意識から消えてしまったほどだ。

大きな瞳と透けた体を持つアオリイカ
これが本当の意味での私とイカとの出会いである。イカを「食べ物」ではなく「生き物」として捉えた初体験だ。ここからは転がるようにイカ沼に落ち、底がないことを悟り、もはや抜け出す気もなく溺れつづけている。
食材、釣りのターゲット、鑑賞対象、飼育対象、アートなどイカの様々な側面や楽しみ方を伝えたくてイカの同人誌を発行したり、経験のなかった釣りに挑戦したり、裁縫を勉強して解剖できるイカのぬいぐるみを作ったり、イカの解剖イベントを開いたりTVに出たりと大忙し。このようにイカ絡みの文筆のお仕事までいただいている。
私の人生はイカ紀元前とイカ紀元後でまったく違うものになってしまった。イカの何がそこまで私を変えたのか。この連載では人生をかけてハマり続けられるイカの魅力と、ハマった人間の可笑しな様子を少しずつ紹介できればと考えている。

衝動で作ってしまった解剖できるイカぬいぐるみ
水族館へ行こう
前段が長くなったが、ここからが今回の本題だ。この「食材から生き物への視点転換体験」を皆さんにも味わってほしいのである。それにはやはり、生きたイカを見ることが一番。というわけで、最もハードルの低いやり方、水族館での鑑賞方法を紹介しよう。既にイカを生き物として見ている人も、これを読めばより一層イカを楽しめるはず。
さて、早くも水族館に行こうと意気込んでくれたあなた。一旦落ち着いてほしい。イカはどこの水族館にでもいるわけではないのだ。水質や水温の変化に敏感なこと、基本的には生き餌を用意する必要があること、そもそも寿命が1年しかないことなど、イカの展示にはいくつものハードルがある。
そのため、常時展示している水族館はまだ多くない。首都圏でイカの常設展示を行っている施設として有名なのはサンシャイン水族館だが、葛西臨海水族園や新江ノ島水族館など期間限定で展示している水族館は増えてきているので、公式SNSなどでイカの展示があるかどうか確認してから行くのがよいだろう。
無事イカ水槽までたどり着いたら、まずは心を無にしてイカと対峙してみよう。イカ水槽付近ではよく「おいしそう」という声が聞こえるが、それはいったん脇においておく。生き物としてその造形や動きを注意深く見ていると「おいしそう」のその先へ心が導かれていくかもしれない。
イカの種類を知る
一口に「イカ」と言っても、種類は様々。世界中で450種ほどのイカが存在すると言われている。小さいものは全長2cmほどのヒメイカから、大きいものは全長10mを超えるダイオウイカまで幅広く、生息域も浅海から深海までと多様だ。
自分が今見ているイカがなんという種で、どこに生息していてどんな暮らしをしているのか、案内板をしっかり読んで観察していると、イカの生き物としての側面が立ち上がってくる。

コブシメ。体の中に石灰質の甲を持つ。全長1mほどになる大きな種
昔と比べ飼育技術が発達したおかげで、水族館で見られるイカの種類はかなり増えた。透けた体と大きな瞳が麗しいアオリイカ、猫のように撫でたくなるコウイカやコブシメ、小さくて可愛らしい姿とは裏腹にエビの中身を溶かして啜るヒメイカ、宇宙を閉じ込めたような輝きで丸くてツルっと吸い込みたくなるミミイカ、南国の花のような姿と地味な岩のような姿のギャップが激しいハナイカなど、イカの多様さには驚かされる。

ミミイカ。体長4cmくらいで、浅瀬でミッキーマウスのような丸いひれをはためかせて泳ぐ
種によっては水族館内で繁殖まで行っており、卵や稚仔の姿、繁殖の様子、老いて死にゆくところまで観察できるのだから素晴らしい。1973年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した動物学者のコンラート・ローレンツ博士は「イカは、人工飼育できない唯一の動物だ」という言葉を残しているが、今や昔。ちなみに、世界で初めてイカの人工飼育に成功したのは日本人の脳科学者、松本元博士である。

ハナイカ。鮮やかな体色が特徴だが、気分が乗らない時は岩のような色。毒がある
イカの体を知る
種類が分かったら、体のつくりを観察してみよう。腕・頭・胴はどのように繋がっているか。目のあるところが頭で、そこから生えているのは腕。見えづらいが腕の中には口を隠している。頭の後ろにある筒状の部分(刺身にして食べるところ)が胴だ。
つまり口で食べたものは頭の中を通り(そのために脳の中央には穴が開いている)胴の中にある胃腸へ運ばれる。頭の中を食物が通っていく感覚はちょっと想像しがたいが、「喉ごし」ならぬ「脳ごし」的なものがあるのだろうか。

腕の中心の丸っこいものが口
続いてヒレ。なじみ深い三角ヒレタイプから、体のふち全体がヒレになっているタイプ、ミッキーマウスのように丸いものがついているタイプなど様々だ。ヒレというと泳ぎに使うものというイメージが強いが、イカの遊泳にはヒレ以外にもう一つ重要なものがある。体の腹側にある筒状の器官、漏斗である。ここから水をジェットのように噴き出して進むのがイカの泳ぎ方だ。この漏斗の向きを調整することで、あらゆる方向に進むことができる。ヒュンッヒュンッという独特の泳ぎが可愛らしくて胸が苦しい。

タコのイラストなどでは口として描かれることが多い漏斗
イカの能力を知る
見どころはまだまだある。イカにはここに書ききれないほどの能力があるのだが、まずは簡単に観察できる体色の変化に注目してみよう。
イカは、体表にちりばめられた「色素胞」という色素の入った粒を収縮させることで色を変えることができる。体色を変えられる動物はほかにもいるが、イカの体色変化のすごいところはそのスピードと多彩さである。瞬きする間に色を変えられるのは、神経伝達の早さの為せる業。
イカは太い神経を持つことでも有名で、この太い神経(巨大神経軸索)を利用してイギリスのアラン・ホジキン博士とアンドリュー・ハクスレー博士が、神経が電気信号を伝達する仕組みを明らかにし、ノーベル生理学・医学賞を受賞している。

赤い粒が色素胞、虹色に輝いているものは虹色細胞と呼ばれている
また、色変化のバリエーションやその意味も多様だ。種にもよるが、例えば褐色、黄、赤など複数の色素を持ち、それぞれの色素胞を重ね合わせることで複雑な色や模様を表現できる。それに加えて構造色を生み出しキラキラと輝く虹色細胞も持ち合わせているので、見ていて全く飽きない。
擬態としての色変化もあれば、驚きや威嚇、求愛の意味で色を変えることもある。特にコウイカやアオリイカについては体色パターンに関する研究も盛んにおこなわれており、成果が待たれる。どんなメッセージを持って色を変えているのか、想像しながら観察すると楽しさ倍増なので試してみてほしい。

餌の投入に驚いたのか、一瞬で真っ黒になったアオリイカ

メスへアピールするための婚姻色。メタリックに輝くカミナリイカの様子
続いて紹介したいのは、捕食の様子だ。もしも運よく摂餌の時間に当たったら、瞬きせずに観察を。大きな瞳で獲物に狙いを定めたら、あとは一瞬。銃のように触腕を発射し、目にもとまらぬ速さで餌を捕まえてしまう。その姿はまさに海のスナイパー。格好よすぎる。たまに失敗するところも愛らしい。

自分の体と同じくらいの大きさのエビを抱えるヒメイカ
餌用のエビや小魚を飼育するコストは非常に高いと聞く。余すところなく食べてほしいが、イカは食べづらい頭や背骨などは外して捨ててしまう。10本の腕で餌を器用に持ち替え、少しずつ噛み千切りながら食べる様子もじっくり観察しよう。
ようこそイカの世界へ
ここまで読んでくれたあなたは、イカを生き物として見る準備は万端だ。これだけガイドをしてきてなんだが、イカの見方はひとそれぞれ。自分なりの視点で観察して楽しんでほしい。そこには広くて深いイカの世界が広がっている。
それでは、水族館でイカを見かけたらちょっと嬉しい気持ちになる人が増えることを願って、この記事を結びたいと思う。次回をお楽しみに!

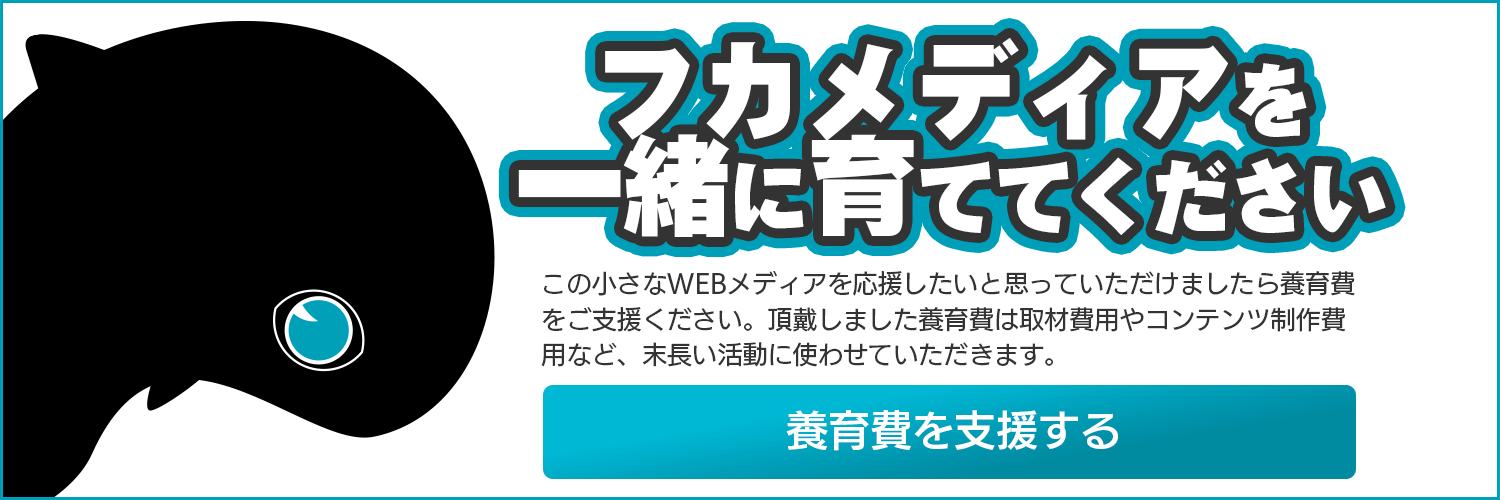
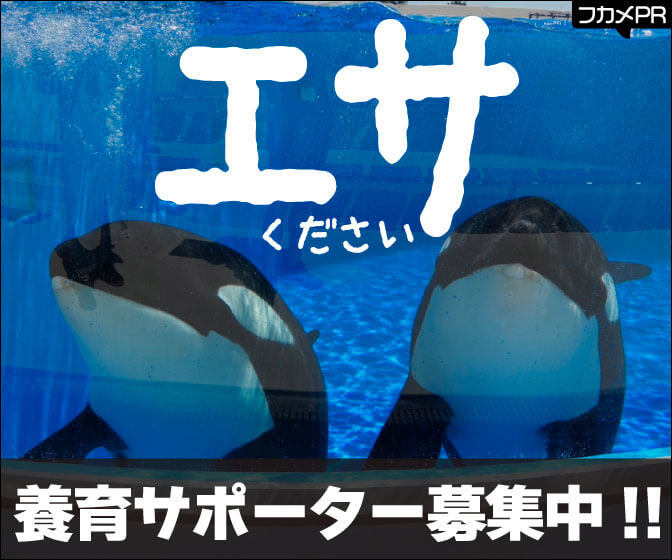
様々なイカ情報もさることながら、それに呼応するイカの超マニアックな部位写真が素敵です
しかしこれはきっとまだまだ序の口なのですね…
これからどんなイカ編愛が繰り出されるのかとても楽しみです